緑内障なら毎日○○歩、歩こう!
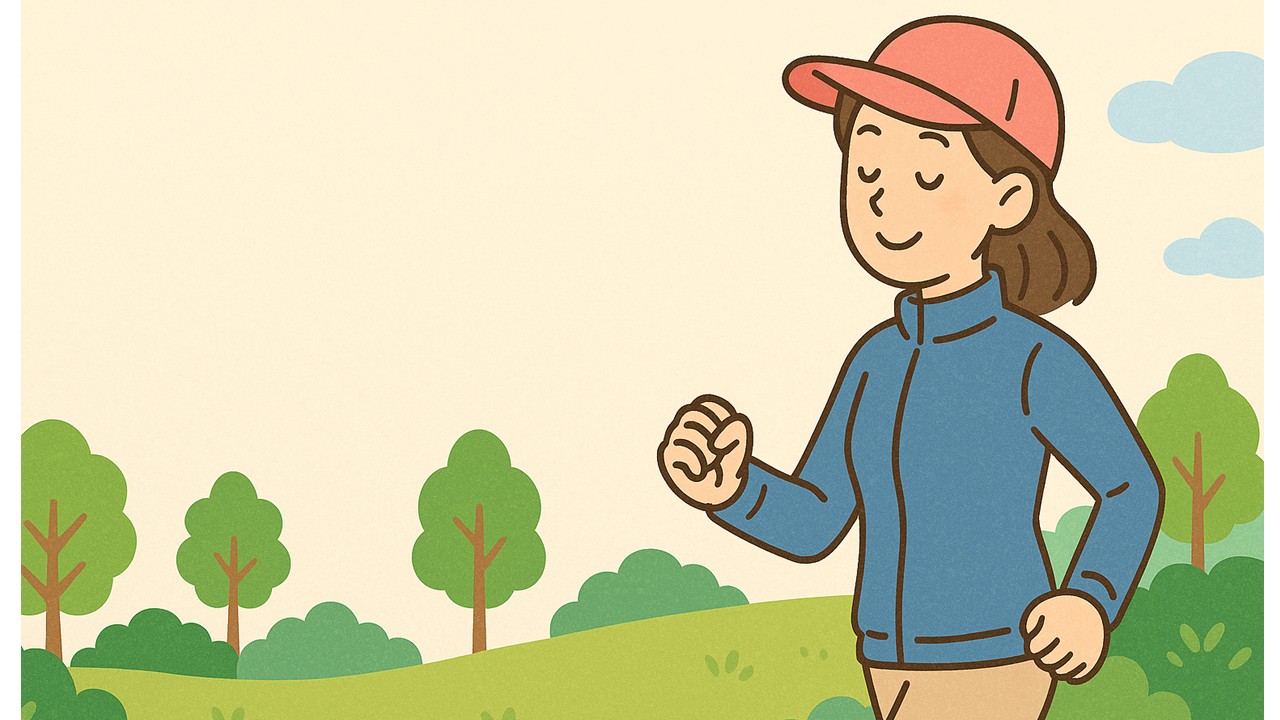
目のために毎日〇〇歩、歩こう!
~ウォーキングが目の健康を守る理由~
はじめに
「運動は体に良い」というのは多くの人が知っていますが、実は目の健康にも大きな影響があることはあまり知られていません。特に緑内障患者さんにとって、日々の歩行習慣は視野の進行スピードを抑える可能性があります。今回は最新の研究をもとに、「緑内障なら何歩歩くのがよいのか」を解説します。
ウォーキングと全身の健康効果
ウォーキングは「最強の生活習慣のひとつ」と呼ばれるほど、多くの健康効果が報告されています。心疾患のリスク低下や糖尿病・メタボの予防、骨粗鬆症の予防、ストレスや不眠、うつ、不安の軽減、さらには認知症の予防や認知機能の改善など、全身に幅広いメリットがあります。がんの予防や死亡率低下にも関係することがわかっています。
例えば、2110人を対象に10.8年間追跡した研究では、1日7000歩以上歩く人は7000歩未満の人に比べ、死亡率が50~70%低下していました。年齢や喫煙歴、既往歴などを統計的に調整しても、ウォーキングだけが死亡率低下と有意に関連していました。ただし、歩けば歩くほど良いわけではなく、効果は1万歩前後で頭打ちになる傾向が報告されています。
糖尿病予防と目の健康
糖尿病は目の細い血管にダメージを与え、糖尿病網膜症や血管新生緑内障を引き起こす可能性があります。スウェーデンの3055人(平均70歳)を調査した研究では、1日6500歩以上歩く人は糖尿病の発症リスクが57%減少し、8500歩以上では63%減少していました。糖尿病網膜症の予防には1日8000歩程度が有効と考えられます。
緑内障と歩数の関係
緑内障は視神経が徐々に障害される病気で、日本人に多い正常眼圧緑内障では血流障害が関与していると考えられています。アメリカで行われた研究(60~80歳の緑内障患者141名)では、普段の歩行数に1000歩加えるごとに視野感度の低下が抑制され、さらに普段より5000歩多く歩くと視野進行が10%抑制されるという結果が示されました。
運動は眼圧を下げ、視神経の血流を改善する可能性があります。また、神経修復に必要なBDNF(脳由来神経栄養因子)を増やす作用も報告されています。
加齢黄斑変性症と運動
15年間の追跡研究では、ウォーキング習慣がある人は滲出型加齢黄斑変性症の発症リスクが30%低下していました。さらに、週3回以上の定期的な運動を行っている人は発症リスクが70%も低くなるという結果もあります。複数の研究をまとめたメタ解析でも、末期の加齢黄斑変性症リスクを41%低下させることが報告されています。
白内障予防にも
運動習慣がある人は、加齢性白内障のリスクが10%減少するとされています。これは運動によって抗酸化酵素が活性化し、水晶体の酸化ダメージを軽減するためと考えられます。
緑内障患者におすすめの歩数
研究結果から考えると、目安としては1日7000~8000歩が最もバランスの取れた歩数です。1万歩を超えても健康効果は横ばいになる傾向があるため、無理に増やす必要はありません。糖尿病や全身疾患の予防も考慮するなら、8000歩程度が理想的です。
歩くときの注意点
急激な運動直後は一時的に眼圧が変動することがあるため、極端な息切れを伴うような無酸素運動は避けましょう。また、屋外でのウォーキングでは紫外線対策としてサングラスや帽子の着用が推奨されます。心疾患や整形外科的な問題がある方は、事前に主治医と相談してから始めることが大切です。
日常に取り入れる工夫
ウォーキングは特別な時間を作らなくても、日常生活に組み込むことができます。通勤で一駅分を歩く、エレベーターの代わりに階段を使う、昼休みに10分散歩する、買い物に歩いて行くなど、小さな積み重ねが歩数を増やします。スマホやスマートウォッチで歩数を管理すれば、モチベーション維持にもつながります。
まとめ
7000~8000歩程度のウォーキングは、全身と目の健康の両方に有効です。糖尿病、緑内障、加齢黄斑変性症、白内障といった疾患のリスク低減が期待できます。特に緑内障では、「普段より+5000歩」が視野進行を10%抑制する可能性が示されています。無理なく、継続できる形で歩数を増やすことが、健康な目を守る第一歩になります。
 058-264-4955
058-264-4955 LINEで予約
LINEで予約