2025年、緑内障治療で新たに承認された、セタネオ®点眼液
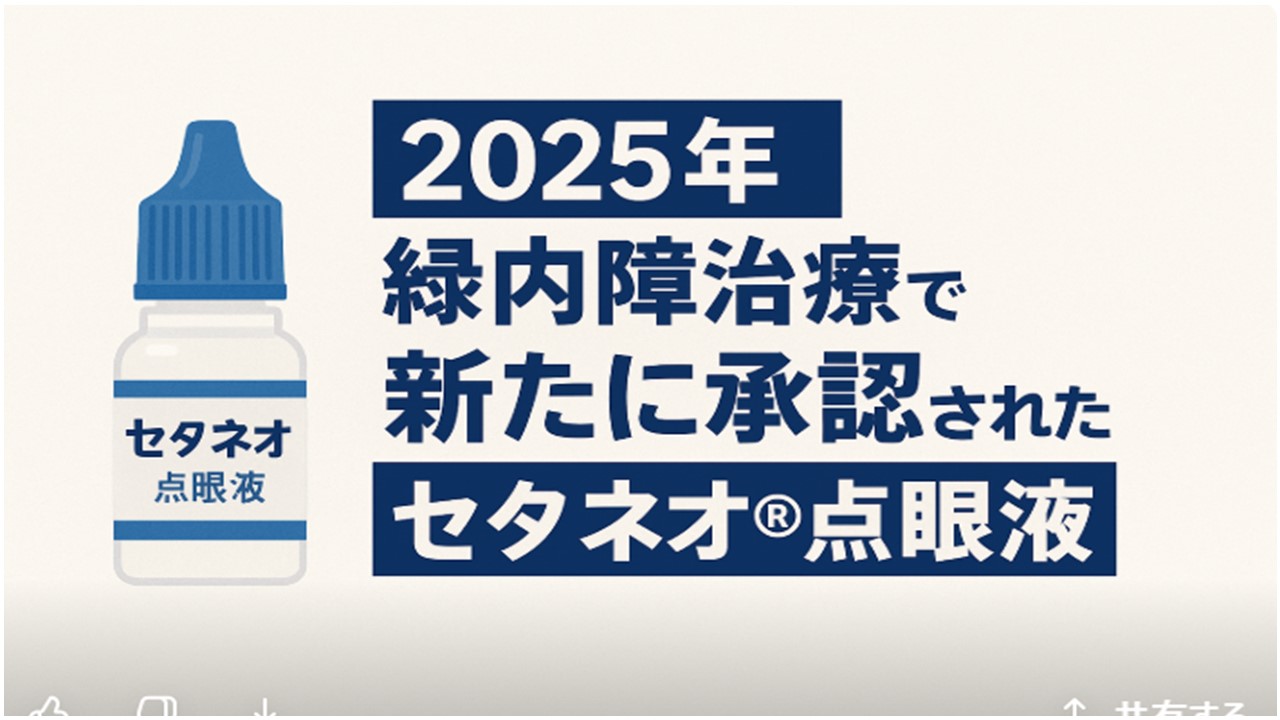
今回は2025年、緑内障治療で新たに承認された、セタネオ®点眼液についてお話しいたします。
緑内障治療は主に目薬による治療が中心となりますが、今年新たな薬が承認されました。
それがセタネオ®点眼液0.002%、一般名:セペタプロストです。日本の参天製薬から今年度末に発売される予定の目薬です。

FP受容体及びEP3受容体に作用する二環式プロスタグランジン誘導体「セタネオ®点眼液0.002%」緑内障・高眼圧症治療剤として国内における製造販売承認を取得、ホームページ上から見れるものです。
今回はセタネオ®点眼液が緑内障治療にどのような新たな価値をもたらすのか、その詳細を詳しくお話しいたします。
まずは基本的な話からですが、緑内障治療の原則は、以前から変わることなく「眼圧を下げること」にあります。これは、世界中の様々な大規模な臨床試験によって、眼圧を下げることで緑内障の進行を遅らせることができる、という事実が証明されているからです。主に目薬

による治療が中心となりますが、その緑内障の目薬は「お水(房水)の排出を促すタイプ」と「お水の産生を抑えるタイプ」の二つに分けられます。さらに、排出を促すタイプの中には、主流出路を広げるものと、副流出路を広げるものの2つがあります。お水の出口は二カ所あるイメージです。目薬を

使うことで、この出口を広げたり、お水の産生を抑えたりして、眼圧を下げています。
緑内障点眼は

大きく分けて6種類あって、まず、最も広く使われているのがプロスタグランジン関連薬です。これには、ラタノプロスト、タフルプロスト、トラボプロスト、ビマトプロストなどがあります。1日1回の点眼で強力に眼圧を下げることができるので、多くの患者さんに第一選択薬として処方されています。副流出路を促すタイプです。

2つ目は、β遮断薬です。チモロールやカルテオロールなどがあって、房水の産生を抑えることで眼圧を下げます。全身への影響、心臓や呼吸器の病気がある方は注意が必要ですが、昔から広く使われてきた実績のある薬です。

3つ目は、炭酸脱水酵素阻害薬です。ドルゾラミドやブリンゾラミドがあり、同じくお水の産生を抑制します。このタイプは副作用が少ないですし、他の薬と併用しながら効果を高めるという目的でよく使われます。

4つ目は、α2作動薬、ブリモニジン、アイファガンが代表的です。他の点眼と比べて眼圧下降効果は同程度だったのに、視野進行はブリモニジンの方が少なかったという結果から神経保護作用も備えているのではないかとされています。
副作用としては、結膜充血のほか、眠気やめまいなど全身への症状が出る場合があるので注意が必要です。

5つ目は、ROCK阻害薬です。日本で開発されたグラナテック®(リパスジル)がこの系統になります。従来の薬は、房水の産生を抑えたり、副流出路からお水を促す作用が中心でした。それに対してグラナテックは、目の中のお水が出ていく主な出口、主流出路の線維柱帯という部分に働きかけて流れを良くするという、これまでになかった新しいタイプの目薬です。

6つ目に、大きく分けるとプロスタグランジン製剤の仲間に入りますが、EP2受容体作動薬という点眼薬です。商品名はエイベリス®です。ラタノプロストのような従来のプロスタグランジン製剤と同等の眼圧下降効果を持ちながらまつ毛が伸びる・まぶたのくぼみ・皮膚の黒ずみといった副作用が起こりにくいのが最大の特徴となります。
また、眼圧を下げる仕組みも従来型とは違うので、ラタノプロストなどで十分な効果が得られなかった方や、副作用で続けられなかった方に新たな選択肢となる薬です。2018年の発売以来、副作用が少ないことから臨床現場でも比較的広く使用されています。
このうち

**セタネオ®点眼液0.002%(セペタプロスト)**は、プロスタグランジン関連薬のグループに分類されます。
というと「今までのラタノプロストやタプロスと同じでなのであまり変わらないのではないか?」と思われた方もいるかもしれません。
ですが、セタネオには従来薬とは大きな違いがあります。
これまで

のプロスタグランジン点眼薬は、主に FP受容体 という部分を刺激して眼圧を下げてきました。
FP受容体が刺激されると、「ブドウ膜強膜流出路」と呼ばれる 副流出路 が広がって、お水の流れがよくなって眼圧が下がります。セタネオは、

このFP受容体に加えて EP3受容体 という別のスイッチも刺激します。
EP3受容体が刺激されると、今度は 線維柱帯、主流出路、 の方の房水の流れも改善されます。
すなわち副流出路だけでなく、主流出路も広げることができるのが大きな特徴です。
簡単に言えば、今まではお水の出口が1つしか開けれなかったのが、もう1つ他の出口も開くようにして流れ出せるようになったというイメージです。
この「2つの作用」によって、今までのプロスタグランジン製剤とはひと味違った位置づけを持っています。
「二つの出口を同時にあけることができる、それなら今まで以上に効きそうだ」と思いますよね。
実際、臨床試験では、従来のプロスタグランジン製剤の代表薬であるラタノプロストと同等の眼圧下降効果が確認されています。つまり「効き目の強さ」という点では大きな差はありません。ですが、作用機序や副作用の特徴が違いますし、眼圧下降効果が大きいので、患者さんによっては第一選択になり得る薬と考えられています。
効き目は同等というと、少しがっかり、それならラタノプロストで充分なのじゃないか?と思うかたもいるかもしれませんが、これは「集団全体で見たとき」の結果です。薬の効き方はすべての患者さんに同じように反応をするわけではありません。個々の患者さんで見れば、ラタノプロストが効きにくい人にセタネオが効く場合も当然あり得ます。もちろん逆もあるわけですが、薬の効き方は個人差があります。そのためラタノプロストと同等の強さをもった、第一選択となる新たな薬が登場したということに自体に大きな意味があります。
使用方法は1日1回で常温保存可能になっています。
1年間にわたる長期投与試験も実施されています。研究からは安定した眼圧コントロール効果が確認されています。
緑内障治療は生涯にわたる長期的なものなので、一時的な効果だけでなく、長期にわたって効果が持続して、安全に使えることが極めて重要です。セタネオ®は、この点においても現状信頼性の高いデータを示しています。
気になるのは副作用ではないでしょうか。従来の

プロスタグランジン製剤は眼圧下降効果が強力な反面、まつげが伸びる、まぶたの皮膚が黒ずむ、まぶたがくぼむといった副作用が出ることがあります。これをまとめて PAP(Prostaglandin Associated Periorbitopathy:プロスタグランジン関連眼周囲症候群) といいます。これらの副作用のために処方しにくい場合がありますが、これはFP受容体を刺激するために出るものです。例えば同じ

プロスタグランジン関連薬のエイベリスはEP2受容体を刺激する作用しかないので、このような事が基本おきないわけです。
ではセタネオ

®はどうなのかというと、有効成分がFP受容体に作用するという特性がありますので、従来のプロスタグランジン関連薬と同じように注意が必要となります。
ですが、セタネオは従来のプロスタグランジ製剤に比べて 黒ずみなどのリスクが少ない可能性が報告されています。もちろん、副作用がまったくないわけではありませんが、「まつげや皮膚の変化が気になる方」や「黒ずみなどで薬を中止せざるを得なかった方」にとって、新しい選択肢になり得ます。
新しい緑内障点眼が発売されたら気になる方も多いと思いますが、全ての方がこちらがいいというわけではもちろんありません。
緑内障治療には、大原則があって「安定している状態なら、治療をむやみに変えない」という鉄則があります。すでに眼圧が安定していて視野も進行していない、副作用も問題ない方は、そのまま現在の治療を継続するのが望ましいです。治療薬の変更は、患者さんの状態に不必要な悪い変化をもたらすリスクがあります。
一方で、どのような方が検討するかというと
まず今のプロスタグランジン製剤で十分な眼圧下降が得られない方です。通常プラスタグランジン製剤から治療をはじめていくことが多いですが、中にはノンレスポンダーといって効きにくい方もおられます。その場合セタネオはFP受容体だけでなくEP3受容体にも働くのでの下がりきらなかった眼圧をもう一段階下げられる可能性があります。特に進行している方や若い方でもう少し下げたいというケースに有効かなと思います。
2つ目は、充血や違和感で従来の薬が続けられなかった方です。先ほども少し話しましたが従来

のプロスタグランジン製剤に比べて、結膜充血が軽度とされる報告があります。ラタノプロストで強い充血が出た人でも、セタネオ点眼液では許容できる範囲に収まるケースは十分あり得るかなと思います。「目薬さすと目が赤くなってしまうからやめたい」と言っていた方に試してみる価値あります。
3つ目はチモプトールやカルテオロールといったβ遮断薬が使いにくい人です。
通常の治療ステップは
① ラタノプロストのようなプロスタグランジン製剤の単剤からはじめて 、 効果不十分なら
② チモロールなどのβ遮断薬を追加するか今だと組み合わさったものザラカムやミケルナといった合剤に変更するという流れが 一般的です。
しかしβ遮断薬は喘息・徐脈や不整脈がある方では禁忌または慎重投与とされています。このため「本来ならプロスタグランジン製剤とβ遮断薬に行きたいけど使えない」という患者さんにはセタネオに変更でもいいと思います。
今後使用される場合は「セタネオ」「タプロス」「エイベリス」などの点眼は、基本的に1日1回タイプが多いですが、就寝前にさすのがおすすめとなります。
これは副作用で多い「充血」が寝ている間に落ち着きやすいからです。ただどうしても夜にさせない場合は他の同じ時間帯に点眼していただければ大丈夫です。ですが1日に2回以上さすと、かえって効果が弱まることがありますのでご注意ください。必ず「1日1回」にしてください。また、どの点眼薬にも共通して大切なポイントがあります。それは
- 点眼後は最低1分間は目を閉じること
- できれば目頭を軽く押さえる(涙点閉鎖)こと
です。
この2つを意識するだけで、薬が目の中にしっかり留まり、眼圧がさらに下がることがあります。 また、薬が鼻やのどに流れて全身に回るのを防げるので、副作用を減らす効果も期待できます。
点眼直後に10回も瞬きをしてしまうと、せっかくの薬が流れ出てしまい、効果がほとんど得られなくなるという報告もされているぐらいです。目薬はたださせばいいというわけではなく、正しい方法でさすことで初めて十分な効果が発揮されるということを知っていてください。
今回の話をまとめますと
- セタネオ®点眼液0.002%は、2025年に承認された新しい緑内障治療薬です。
- 従来のプロスタグランジン関連薬と同様に1日1回の点眼で、強力な眼圧下降効果を発揮します。
- 最大の特徴は、FP受容体とEP3受容体の両方に作用するというユニークなメカニズムです。
4 臨床試験では、ラタノプロストと同等の効果が示されました。 これはセタネオ®が第一選択で使える薬であることを意味します。
5 副作用は従来のプロスタグランジ関連薬と似ていますが、新しい作用機序を持つことで、治療の選択肢を大きく広げる存在となります。
今後は、どのような患者さんにセタネオ®が特に有効なのか、また、他の薬との併用効果はどうなのか、といった点がさらに明らかになっていくと思います。将来的には、遺伝子情報によって、最初からセタネオ®が第一選択薬となるような時代が来るかもしれません。今回は新しい緑内障点眼セタネオ点眼についてお話しいたしました。
 058-264-4955
058-264-4955 LINEで予約
LINEで予約