2025年発売予定 多焦点眼内レンズ
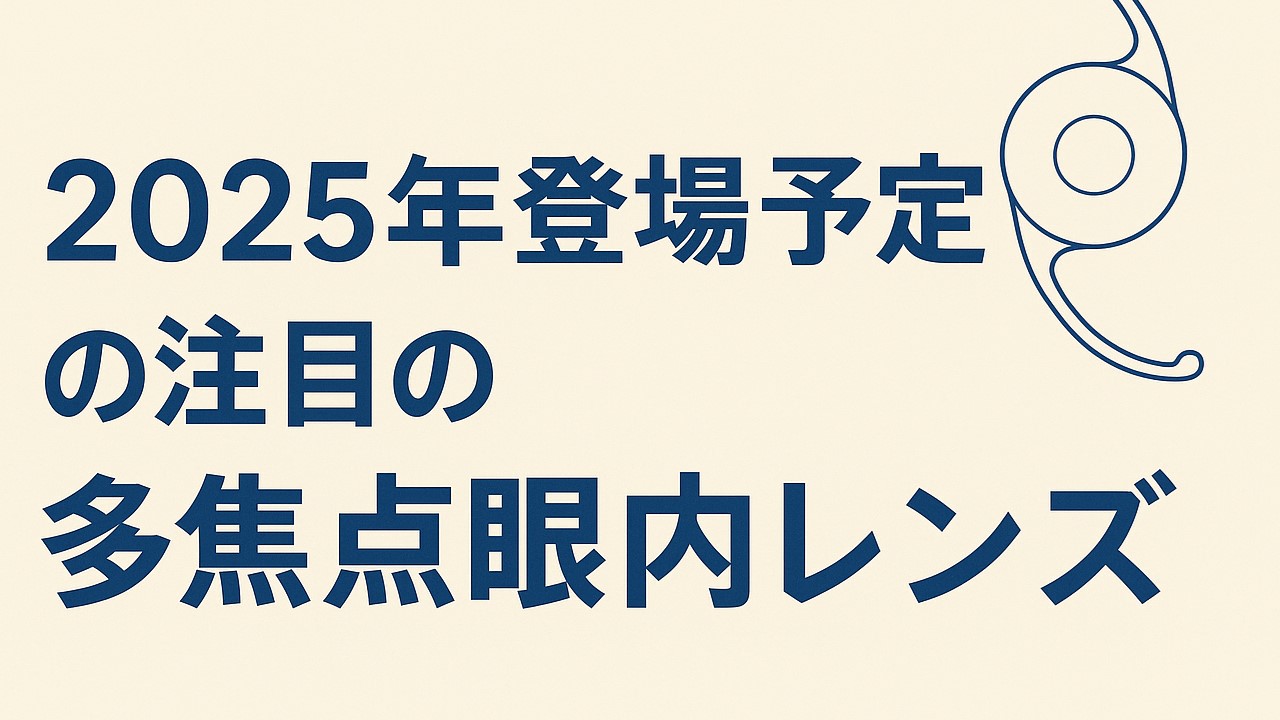
今回は2025年に発売予定の新しい多焦点眼内レンズに関してお話しいたします。
2025年も、白内障手術を受けられる方にとって、より良い選択肢となる新しい多焦点眼内レンズが続々と登場してきています。一方で「色んなレンズが出てきてどのレンズが自分に合っているのか?」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
今回は、2025年に登場する注目の新しい多焦点眼内レンズについて、その特徴、選び方のポイント、そして具体的なメリット・デメリットに関して詳しく解説いたします。
1.Vivityトーリック(乱視用)
まず、最初にご紹介するのは、選定療養で使用可能なVivity(ビビティ)のトーリックモデル、つまり乱視矯正機能があるレンズに関してです。2025年5月12日に待望の発売を迎えました。これまで、乱視をお持ちでVivityに関心をお持ちだった方にとっては、待ちに待った登場ではないでしょうか。
クラレオンビビティ(Clareon Vivity)は、ALCON(アルコン)社の非回折型の焦点深度拡張型の眼内レンズです。アメリカでは2020年から、日本国内においては、2023年に厚生労働省の承認を得て、使用が開始されていて、その高い臨床成績が広く知られています。
Vivityの最大の特徴は、独自のX-WAVEテクノロジーというものによって、回折構造を用いずに焦点深度を拡張している点です。この特殊な技術によって、単焦点眼内レンズのような自然な見え方を維持しながら、遠方から中間距離、だいたい50cmまで連続的に焦点を拡張することを可能にしています。
遠方から中間距離にかけての見え方が非常に自然であると同時に、夜間の運転時などに気になるハロー(光の輪)やグレア(光のまぶしさ)の発生が大幅に抑制されるという大きな利点があります。今までの多焦点眼内レンズは、「見える範囲は広がるものの、見え方の質が低下する」という、いわばトレードオフの関係が避けられませんでしたが、Vivityはそのようなデメリットを最小限に抑えつつ、焦点深度を広げることができる、非常に完成度の高いレンズと言っていいと思います。
しかしながら、これまでのVivityには、乱視を矯正する機能を持つトーリックモデルが存在しなかったので、乱視をお持ちの方でVivityを希望されても、その使用を諦めざるを得ないというケースが少なくありませんでした。従来のVivityの適応は、手術前に予測される術後の残余乱視が-0.5D(ディオプター)以下の患者さんに限定されていて、術前から中等度以上の乱視をお持ちの方には、その使用を控える必要があったんですね。実際に-0.75Dより大きな乱視をお持ちの患者さんは決して少なくないので、Vivityを選択する上で大きな課題になっていました。
待たれた方も多くおられると思いますし、多くの乱視がある患者さんにもVivityが選択肢できるようになったことは、本当に良いことだと思います。
ただし、Vivityは、

遠方から中間距離にかけて優れた視力を提供する一方で、近方視力、

特に40cm以内での視力を強く必要とする方にとっては、老眼鏡の併用が必要になる場合があります。そのため、読書や手芸、模型作りなど、手元での細かい作業が多い方にとっては、少し不便を感じる可能性がある、場合によっては単焦点で手元に合わせた方がよいことは理解しておく必要があります。
2.PureSee(ピュアシー)
次にご紹介するのは、Johnson & Johnson(ジョンソン・エンド・ジョンソン)社が開発した、最新の焦点深度拡張型(EDOF)眼内レンズ、テクニスピュアシーです。
現時点では、日本ではまだ正式に発売されていませんが、この夏の発売が予定されていて、大きな注目を集めています。海外ではすでに多くの臨床データが報告されていて、術後の視力の成績や満足度について、非常に高い評価を得ています。
テクニスPureSeeは、Vivityと同様に非回折型であり、光を回折させる構造を一切持たない、純粋な屈折型設計であることが大きな特徴です。回折構造を持たないため、光のエネルギー分散によるコントラストの低下や、ハロー、グレア、スターバーストなどの光視症を最小限に抑える設計となっています。
Vivityに採用されている波面制御型の光学構造など、詳細な設計については、現時点では公表されていませんが、海外の臨床データからは、50cm程度までの中間距離まで滑らかな焦点深度を持ちつつ、遠方視力も良好で、非常に自然な見え方が得られるという報告が多数されています。
海外の臨床研究

で報告されている、PureSeeを挿入した症例における平均的な視力データは以下の通りです。
遠方視力は1.2で、良好な遠方視力が得られています。
50-70cmの中間視力は0.8程度でした。
40cmの近方視力は0.4程度でした。
また、焦点深度に関しては、有効視力とされる0.6を維持できる範囲が、焦点のピークから近方方向に-2.00D付近まで広がっていると報告されています。
これは、おおよそ約50 cm以降遠方は良好な視力を確保できることを意味します。
グレアやハロー、コントラスト感度の低下といった視覚的な副作用も、PureSeeでは極めて軽微であると報告されています。
これらの臨床結果から、PureSeeは、ハロー・グレアに対する許容度が低い方や、夜間の運転を重視する方にとっても適したレンズとして、総合的に高い評価を得ています。Vivityと同等の高性能レンズと考えて頂いてよいと思いますね。
ただし、PureSeeもVivityと同様に、40cm以内の近方の視力はやや低下する傾向があります。そのため、編み物や裁縫、細かい手作業など、日常的に近距離での作業が多い方にとっては、老眼鏡の併用が必要となる可能性があることは考慮しておく必要があります。
現時点では、VivityとPureSeeを直接比較した臨床論文はありませんが、どちらも非常に質の高いレンズであると考えられます。あえて検討する点があるとすれば、PureSeeはVivityと比較して臨床での使用期間がまだ短いので、国内の長期的な臨床データが少ないという点が挙げられます。また、Vivityトーリックモデルは、一部の度数ではまだ乱視用レンズがカバーしきれていませんが、PureSeeは、全度数において乱視矯正モデル(トーリックレンズ)が用意される予定です。Vivityもほとんどの度数はカバーされていますので通常は問題になりませんが、特に遠視が強く、かつ乱視も強い方の場合、Vivityトーリックでは対応できる度数がないかもしれません。その場合Pure seeなら対応できるということがあるかもしれません。
3.Gemetric Plus(ジェメトリックプラス)
次に紹介するのは、日本のHOYA株式会社が開発した多焦点眼内レンズ、**Gemetric Plus(ジェメトリックプラス)**です。このレンズの最も大きな特徴は、他の多焦点眼内レンズと比較して、近方を重視した設計になっている点です。ジェメトリックプラスは、近方、具体的には約30〜40cmの距離での視力を重視していて、読書やスマートフォン、タブレットなど、手元の作業をより快適に行えるように設計されています。
このジェメトリックプラスは、昨年発売されたHOYA社の多焦点眼内レンズ、**Gemetric(ジェメトリック)**と、いわば兄弟のような関係にあります。HOYA社では、「ペアリング」という概念をあげていますが、この2種類のレンズを片目ずつ組み合わせて使用することで、遠方から近方までの視力をバランス良く見えるようにするという意図があります。
詳しい方の中には、「ペアリング」と「ミックス&マッチ」はどう違うのか?と思われた方もおられるかもしれません。左右の眼に異なる特性を持つレンズを組み合わせることで、それぞれのレンズの利点を活かして、欠点を補なおうとする基本的な考え方は共通しています。通常「ミックス&マッチ」は、異なるメーカーのレンズや、異なる光学設計、例えば、VivityとPanoptixといったレンズを組み合わせる場合に用いられることが多いです。一方、GemetricとGemetric Plusのペアリングは、同一メーカーのレンズであり、レンズの材質はもちろん、基本的なレンズの設計が同じであるため、よりバランスの取れた見え方が期待できると考えられています。
具体的には、遠方視力を重視した設計のGemetricを片眼に、そして近方視力を重視したGemetric Plusをもう片眼に挿入することで、両眼で見た際に、遠方から近方まで、より広い範囲で快適な視力を得ることが期待されます。多焦点眼内レンズは、近方視力に対する満足度に個人差が見られることがありますが、レンズを組み合わせるという選択肢をとることで、より個々のニーズに合わせた見え方を実現できる可能性があります。もちろん、別々に入れることを推奨しているわけではなく、片眼に挿入したGeometricで近方視力が十分に得られていると感じる場合は、無理にGeometric Plusを選択する必要はありません。もう片眼にもGeometricを選択するということでよいと思います。
中には、「遠くの見え方はそれほど気にしないから、とにかく近くをしっかりと見たい」という方もいらっしゃるかもしれません。そのような場合、「最初から両眼ともジェメトリックプラスを選べば良いのでは?」と思われるかもしれませんが、近方視力に重点を置いた多焦点眼内レンズは、一般的に遠方視力やコントラスト感度がやや犠牲になりやすい傾向があります。そのため、両眼にGeometric Plusを単独で使用した場合、「全体的に少しぼやけたような見え方になる」と感じる可能性があります。このため、既にGeometricが片眼に挿入されていて、更なる近方視力の改善を希望するという場合にGeometric Plusを検討するというのがよろしいと思います。
4.Galaxy(ギャラクシー)
最後に、全く新しいコンセプトを持つ多焦点眼内レンズとして、Galaxy(ギャラクシー)をご紹介いたします。
このレンズは、AI(人工知能)によって設計された世界初の多焦点眼内レンズとして登場し、大きな注目を集めています。
Galaxy

の最大の特徴は、その光学構造にあります。従来の多焦点レンズの多くは、遠方・中間・近方といった異なる距離にピントを合わせるための焦点を、同心円状に配置していました。この同心円状の構造が、光の回折現象を引き起こし、ハローやグレアといった夜間の見え方の問題の原因となることがありました。
これに対してGalaxyは、全く新しい発想に基づいた回折構造ではない「スパイラル(渦巻き)構造」を採用しています。
このスパイラル構造の大きな利点は、遠く、中間、近く、すべての距離からの光がバランス良く網膜に届くことです。これにより、

従来の同心円状のレンズで課題となっていた、光のにじみ(ハロー・グレア)がほとんどなくなり、単焦点眼内レンズに近い、自然な見え方になっています。
また、従来の多焦点眼内レンズのように、特定の距離に焦点があるというわけではなく、スパイラル構造によって**「連続的な焦点」を可能にしているので、見たい距離にスムーズに視線を合わせることができて、見え方の違和感が少ないという点も大きな魅力です。
さらに、Galaxy

は高コントラスト設計にも配慮されていて、暗い場所や夜間の見え方にも強いとされています。従来の回折型レンズで見られたような、「見えるけれど、はっきりしない」という不満を軽減できるように様々な工夫がされています。臨床データによれば、ハロー・グレアはほとんど見られず、コントラスト感度も単焦点眼内レンズと同等レベルでありながら、近見は40cm以降スムーズな見え方が期待できると報告されています。見える範囲

に関しては3焦点には及ばないけど、焦点深度拡張型タイプよりは近見が得られやすいイメージです。
Galaxyは自由診療のレンズではありますが、従来の回折型多焦眼内レンズにはない全く新しい発想に基づいて設計されたレンズであり、今後の多焦点眼内レンズの可能性を示すものとしてピックアップさせていただきました。今後、AI技術の進歩などによって、さらに斬新な設計の眼内レンズが登場するかもしれません。
今回の話をまとめますと
- 2025年5月からクラレオンビビティが発売になりました。
- 2025年夏頃テクニスPureSeeが発売される予定 非回折型、純屈折型の焦点深度拡張タイプのレンズでVivityとほぼ同等の性能をもっています
- Geometric Plusは多焦点眼内レンズの中では珍しい近方重視型のレンズで、従来のGeometricとの“ペアリング”で広い焦点範囲をカバーすることが期待されています。
- Galaxyは世界初、AI設計+スパイラル構造の多焦点眼内レンズ 40cm以降遠方が見やすいというのが特徴です。
これまでは、多焦点眼内レンズにはメリットだけでなくデメリットもあるため、積極的に勧めにくいケースもありました。しかし近年は、そうしたデメリットが軽減されたレンズが増えてきている印象があります。眼内レンズの種類によって術後の見え方は大きく異なりますので、興味のある方は今回の内容をぜひ参考にみてください。
今回は、2025年に登場予定の注目の多焦点眼内レンズとして、Vivityトーリック、PureSee、Geometric Plus、そしてGalaxyの4種類をご紹介しました。
 058-264-4955
058-264-4955 LINEで予約
LINEで予約